
今日は、映画「パーマネント野ばら」の初日でした。
吉田大八監督は、大学の自主映画のクラブの後輩。
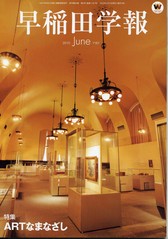
先日は、「早稲田学報」なる雑誌に、一緒に登場しました。


左から、TBSのキャスターの松原耕二氏、吉田大八監督、自分、映画「カイジ」「ごくせん」監督の佐藤東弥くん。
並んで写真を撮ってもらい、短い記事は私が書きました。
1980年代、早稲田で自主映画を撮っていた仲間のその後です。(3人が、40歳過ぎてから映画監督になり、ひとりはキャスターになりました…というお話)
このとき、大八くんから、この映画の話を聞いていたので、早く見たくてしかたなかったです。試写で少し前に見たのですが、公開に合わせて感想を書こうと思って、今日になりました。
とても優しい映画です。
色使いも演出も音楽も。実際は、かなりきついお話なんですが、それをうすいオブラートのようなもので包んでいる。だから、ぐさっと刺すようなシーンも、血が流れないようにできています。そして、ラストには思いもしなかった展開があります。あるいは、ヒミツが暴露される…というのかな。
正直、自分は、まったく、この展開が予想できませんでした。割となんでも、物語の構造を予想してしまうたちだというのに。
では、なぜ、自分がこの展開、結末を予想できなかったかについて、書きましょう。今日は、大丈夫です。ネタばれはありません。…たぶん。
私は、この映画を、「女の子の恋に関する物語」と考えて観に行きました。映画のチラシにもそんなことが書いてあったから、「恋」や「愛」に関するお話だと思っていたのです。だから、あの結末を予想できなかった。
けれども。私は、この映画は、レンアイに関する映画ではないのではないか…と思っています。ひとびとの思いやりに関する物語なんです。たぶん、この時のひとびととは、女性たちのことをさすのかもしれない。
私が思い出したのは、「ラースとその彼女」という映画でした。等身大の人形(ダッチワイフ)を自分の恋人と思いこむ、ラースという青年の物語です。物語の結末で、ラースを慰めるおばあさんたちが出てきます。傷ついたラースを囲み、お茶を飲んだり、編み物をしながら、ただ、ひたすら一緒にいる。他愛のない話をする。そのとき、その中のおばあさんが、こんなことを言うんです。
「誰かが傷ついた時には、ただ、そばにいてあげるの。ただ、じっとね。あとはなにもしなくていいのよ」
そんなセリフです。「パーマネント野ばら」を見て、そのセリフを思い出しました。
いえ、映画を見終わった後には、にわかにはわからなかったです。ダメな男ばかり好きになってしまう女の物語かと思っていたからです。私もある意味、だめんずうぉーかーでしたから、そういう目線で見ていました。
けれども、時間がたつうちに、この映画が提示しているものは、そんな、「ダメな男ばかり好きになる、どうしようもない女たちの話」ではないのではないか。
これは、傷つき、弱り、まともな考え方ができなくなってしまったひとが帰る場所についてのお話なんだ。そんなひとを優しく受け入れる場所があるし、受け入れてくれるひとがいるし、そこでは、なにが正しいかなんてこと、どうでもいいじゃないか…ってことなんです。
そこでは、同じような痛みを持ったひとたち(女たち)が、寄り添い、美容院に通い、他愛のない話をして笑い、でも、傷をえぐるようなマネだけは絶対しない。それぞれの不幸を言い当てたりしない。
近代というのは、(って大きく出ましたけど)、結婚制度が張り巡らされ、幸せな結婚、まともな人生が求められてきたけど、なんか、それは正しいかもしれないけど、それから落ちたひとへの配慮が足りなかったように思う。浮気されたら離婚して、もっといい相手を探す。もっといい仕事、もっといい結婚。前進することが「善」である社会。
そういう世界に、小さな声で、「NO」いや、「あかん…」と言っているような気がしました。
ある種のファンタジー、女性たちの優しい王国がそこにはありました。
だって、本当の田舎だったら、もっと、「イヤなおばちゃん」「PTA的な考えをもった奥様」たちが必ずいるはず。結婚制度や一夫一婦制を強烈に支持するようなひとたちがね。
でも、ここには、そんなひとはいないんです。実はラジカルなおばちゃんたちの巣窟なんです。そこでは、不幸が不幸じゃなくなる、魔法が取引されているんです。
そこが「パーマネント野ばら」の魅力だと思いました。